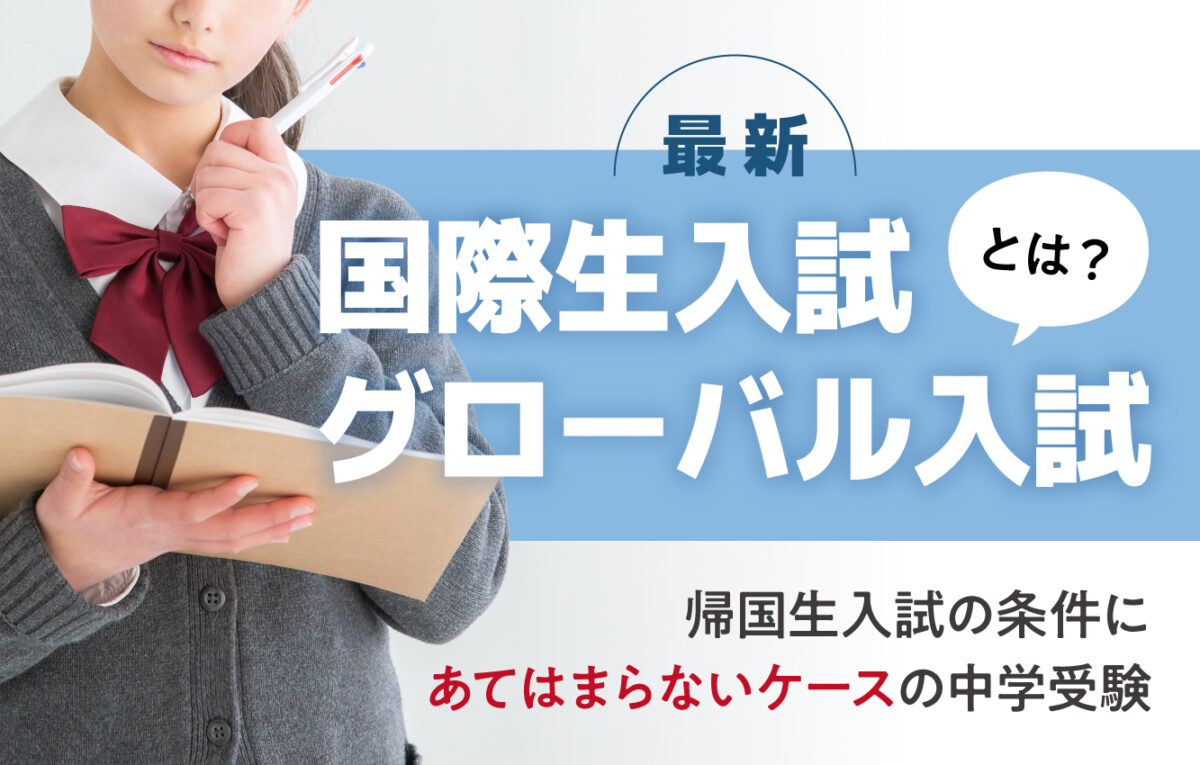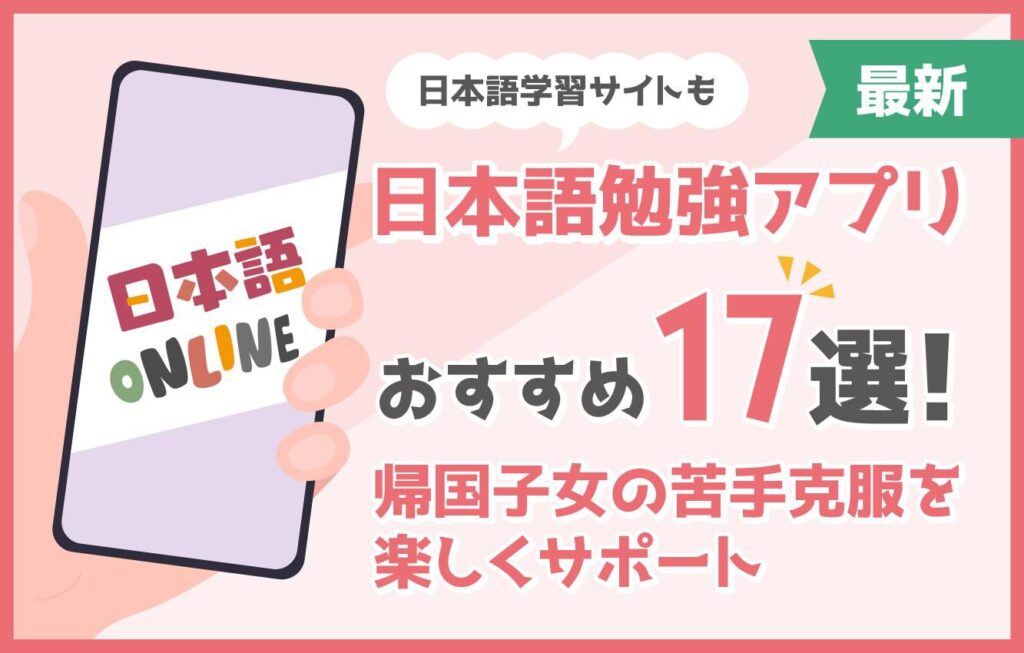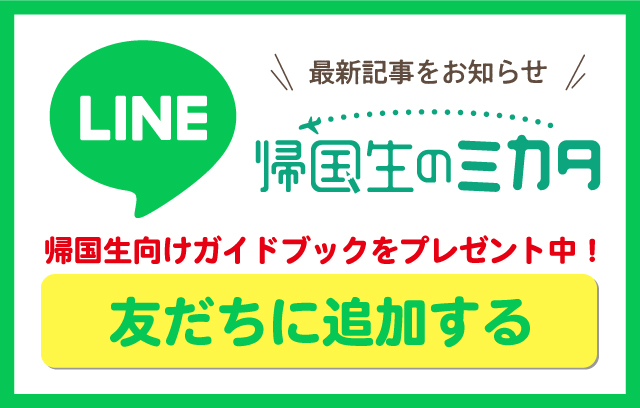帰国子女だから実践したい作文対策!書く習慣をつける実践的な対策を解説
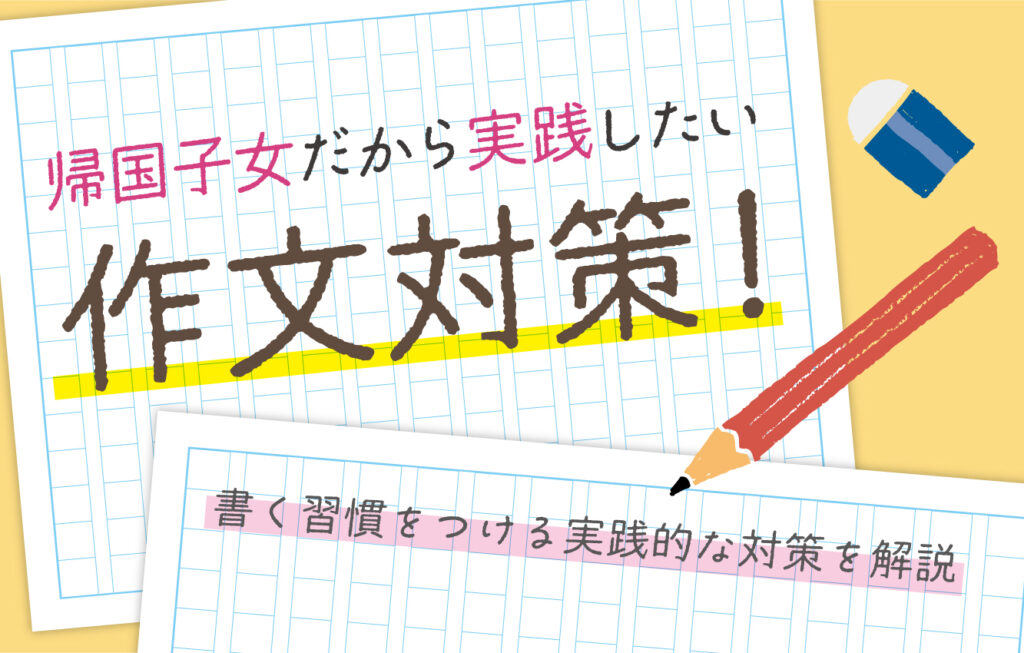
帰国子女向けの作文入試は、作文を通じて生徒の基礎学力を測るとともに、家庭での教育力を見るという目的もあって実施されています。作文入試は、ご家庭での親子一丸となった対策が不可欠な科目です。本記事では、お子様の書く習慣が身につくような実践的な対策をご紹介いたします。
帰国子女向けの作文入試とは
帰国生入試では帰国生枠と呼ばれる受験枠もあり、学校によって科目が異なり、作文科目も試験に組み込まれていることもあります。帰国生枠を利用することで、一般入試に加えて受験のチャンスが増えますので、しっかりとした対策が不可欠です。
まず、帰国生枠で受験可能な一般的な条件は以下の通りです。
| ① 日本に本帰国してから約3年以内であること ② 海外に1年以上在住していたこと(期間が継続か通算かは、学校によって違います) ③ インターナショナルスクール・現地校で9年の学校教育課程を修了、あるいは修了せず帰国し日本の中学校へ編入、卒業見込み などです。 |
ただし、学校によって他の条件が加わる場合もありますので、各学校の条件を必ず確認してください。
また、帰国生が受験する科目も学校によって異なり、大きく以下のような受験科目があります。
| ① 国内一般入試型(3教科・5教科) ② 英語力特化型(英語高配点・英語のみ・英語検定必須など) ③ 面接・小論文+教科など |
特に③のタイプの入試の場合には作文対策が重要となります。どの言語なのかなどを確認し、指導経験のある人から指導を受けるようにしましょう。
作文の書き方
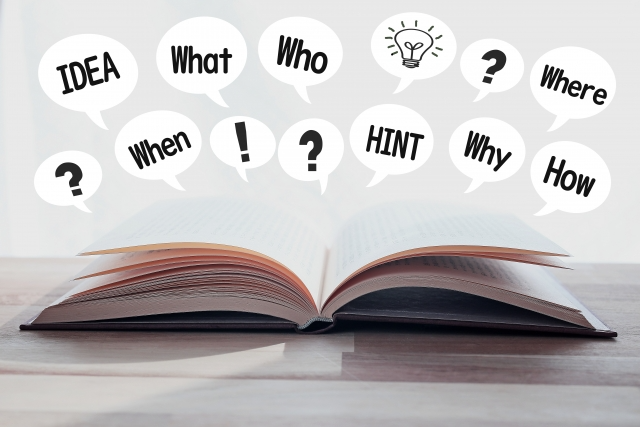
作文を書く場合、思いついたことを上から冗長に書くのではなく、構成や基本的な事項をおさえて書くことが重要です。
まず、日本語で分かりやすい文章を書くためには、よく5W1Hと呼ばれるような「いつ、どこで、誰が、なんで、どうしたか」という点を意識して書くように練習しましょう。
日本語を書くことに慣れていない帰国子女の方は、相手に伝えるために不可欠な情報が欠けてしまう傾向があります。そのため、自分と同じ経験をしていない相手にも状況が想像できるような情報を漏れなく入れる必要があります。
また、作文の構成は「意見、理由、体験内容、まとめ」+誤字脱字の確認、という順番で書きましょう。自分が一番述べたい意見(結論)を先に持ってきて、その後ろにそれを支える具体的な理由や体験内容を盛り込むという形式です。
結論を先に持ってくることで、読み手に自分が何を一番伝えたいのかを真っ先に伝えることができます。
帰国生作文入試の出題例
帰国生作文入試にはある程度、典型的な問題の出し方があります。文字数や時間は学校によって異なり、400~600字という課題が一般的ですが、なかには1,000~1,200字という学校もあります。
具体的な出題例は以下の通りです。
| ◉日本と、あなたが暮らしていた国の一番の文化のちがいは何ですか ◉海外生活を通して乗り越えたことは何ですか ◉あなたが暮らしていた国で身につけた力は何ですか、またそれを日本ではどのように活かせますか ◉他者の立場に立つとはどのようなことですか ◉あなたが今まで経験した中で最も難しかったことについて教えてください。また、それをどのように克服しましたか?誰かに協力してもらったり、誰かと助け合った様子なども含めて具体的に●●字以内で書いてください |
帰国子女だからこそしたい対策
帰国子女は海外に暮らしていたため、日本語を書き慣れていないことも多いでしょう。そのため、以下の基礎的な事項をおさえて日本語の作文に慣れましょう。
◆漢字を正しく使う
日本語の作文を課している学校の中には、国語力をみている学校も多くあります。日々の漢字学習の中で、正しく書くことや送り仮名などを意識して覚えるようにしましょう。学校によっては、とめ、はね、はらいなどの字の書き方を細かく見るところもあります。
◆原稿用紙の使い方を知る
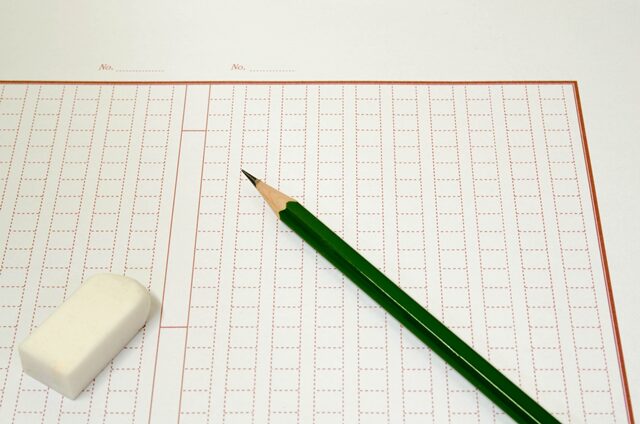
解答用紙の形式についても慣れておくようにしましょう。解答用紙が罫線の場合もありますが、日本語特有の縦書きの原稿用紙の場合もあります。日本語の原稿用紙の場合は、独自の決まりがありますので、試験でも実践できるように覚えておきましょう。
| ◉題名は1行目に3マスあけてから書きましょう ◉名前は2行目に書き、下が1マスあくようにしましょう ◉本文は4行目から書き始め、3行目はあけておきましょう ◉段落の初めは1段下げましょう |
◆日本語の語彙を強化する
海外で長く生活していると、日本語の語彙が不足してしまうおそれがあります。海外経験を表現力豊かに書くためにも、海外にいる時から日本語の語彙を増やす活動をすることが不可欠です。
たとえば、日本語で日記を書く、日本語の本を分野問わず読む(小説・時事など)、家族とある課題やニュースなどについて議論するなどです。
普段からできる作文対策
作文対策は一朝一夕にできるものではなく、長期的な対策と積み重ねが重要です。ここでは日々、少しの時間でも取り組めるような対策をご紹介します。
◆日記をつける
異文化体験を作文の中で活かすためには、日々の暮らしの中で五感を使って感じたことや学んだことを少しずつ記録しておき、具体的なエピソードを蓄積しておくことが大事です。毎日・毎週日記を書き、具体的なイベントと感想を記しておきましょう。
また、カテゴリーに分類して日記を書くことも効果的です。たとえば、「学校生活」「日常生活」「言語・コミュニケーション」「行事・イベント」などに分けてみましょう。そして、体験を写真やビデオで保存しておくことも良いでしょう。これらのメディアに対してメモ書きをつけておくと後から思い出しやすくなります。
◆家族や友達と話す
家族や友達と異文化体験について話し合うことも、エピソード整理のうえで非常に役立ちます。他者と話すことによって、自分だけで整理する中で気づけなかった側面や視点を得ることができます。思いがけないアイデアに遭遇することもあります。これらのアイデアについても記録しておくとあとで見返すのに役立ちます。
◆定期的に文章を書く時間を確保
作文問題を時間内に書きあげるためには、普段から文章を書き慣れておくことが基本的な対策です。書きあげることで精一杯になるのではなく、内容や構成を考えながら書くためには、書きながら読み返したり見直したりする回数を減らすことが大事です。
消しゴムで消して書き直すだけでも時間のロスにつながるため、書き直す必要のない文章を最初から書けることが重要です。そのため、どのような文章でも良いので、普段から文章を書く時間を家族で作ることが重要です。
実践的な作文練習・受験対策
ここからは、いざ作文試験の対策を本格的に始めるというときの、試験対策のお話をご紹介いたします。
◆キーワードを元に作文を書いてみる
作文を実際にテーマに沿って書くためには材料が必要です。上で述べたような日記や家族との議論などを通して出てきた「何を書きたいのか」というキーワードを見つけてみましょう。その中で海外生活ならではのキーワードも出てくるでしょう。
学校生活の中で、たとえば「クラブ活動」「異文化」「友情」などのキーワードが出てきたらそれを用いて書きあげてみましょう。
◆モチベーションを上げる

作文試験は自分だけで完結するものではなく、相手に見てもらうということを忘れずに読む相手のことも考えながら書くようにしましょう。時には、自分の祖父母や両親、親戚に手紙を書くなどして相手に見てもらう機会を増やすことも大事です。
読む相手の存在があることで、文章を書く目的意識も形成され、モチベーションもあがるでしょう。
◆添削・リライトする
作文の練習段階では、書いて書きっぱなしではなく、必ず他者の目を通して自らの間違いに気づくことが大事です。まずは、誰かに添削してもらい、その後に添削結果をもとに、リライトしてみましょう。リライトまでいかなくても、添削結果に沿って間違いを直すだけでも、自分のミスの傾向や正しい文章を学習するために効果があります。
◆過去問を解く
ある程度文章を書くための基礎作りができた段階で、志望校や志望校以外でも類似の問題を出題している学校の過去問を解いてみましょう。過去問の指定字数・時間内で解き終われるように練習をしてみることが大事です。解答用紙も、実際の様式があればそれを使い、なければ類似したものを用意して練習しましょう。
書く習慣をつけ表現力を磨いて作文試験に挑もう
日本を離れて海外で暮らしている皆さんは、人生の中で特別な体験をしている時期にあります。これらの特別な体験を共有し、理解してもらうことが作文試験において重要な目的です。日本語でこれらの「特別」な体験を普段から記録し、日本語力を磨きながら試験では他者にシェアするという意識を持って文章を書けるようにしましょう。
●記事内容は執筆時点の情報に基づきます。
【関連記事】
最新情報をLINEとメルマガでお届けしています!ぜひお友だち追加・フォローしてください。