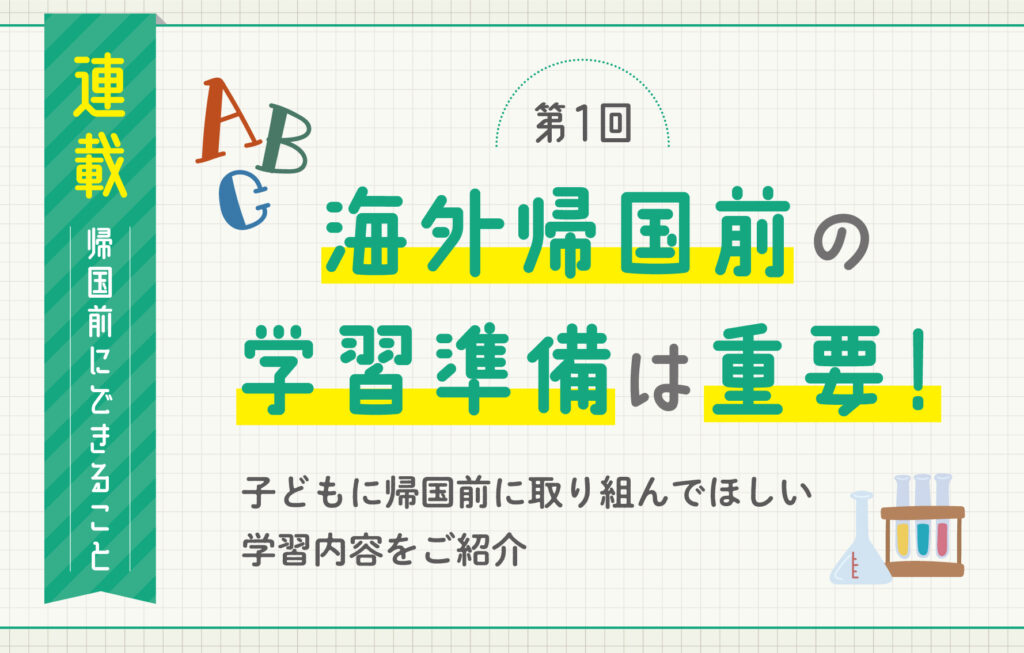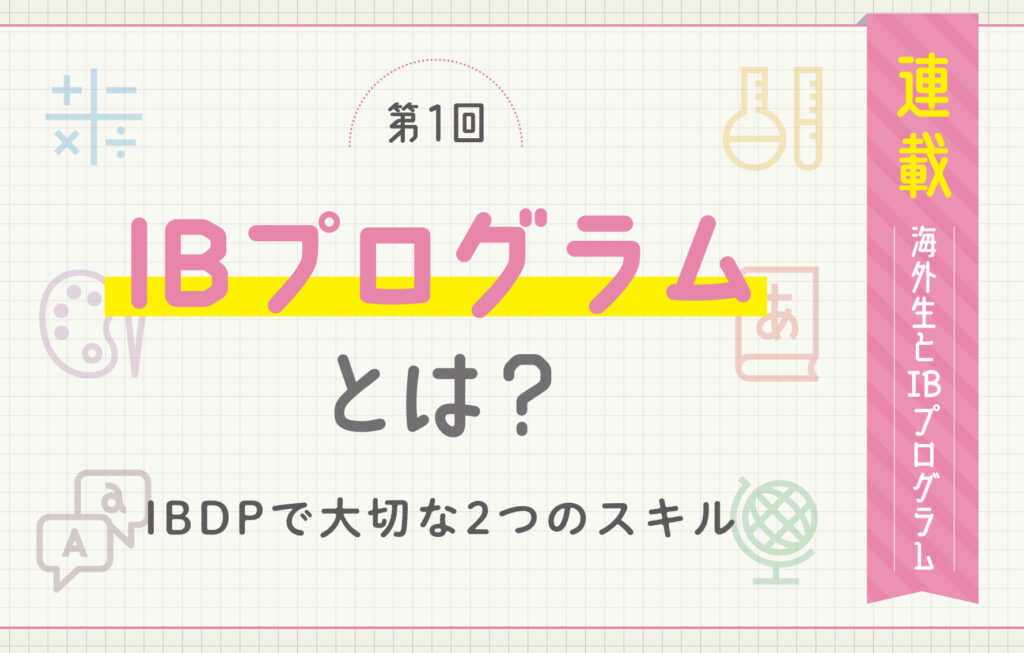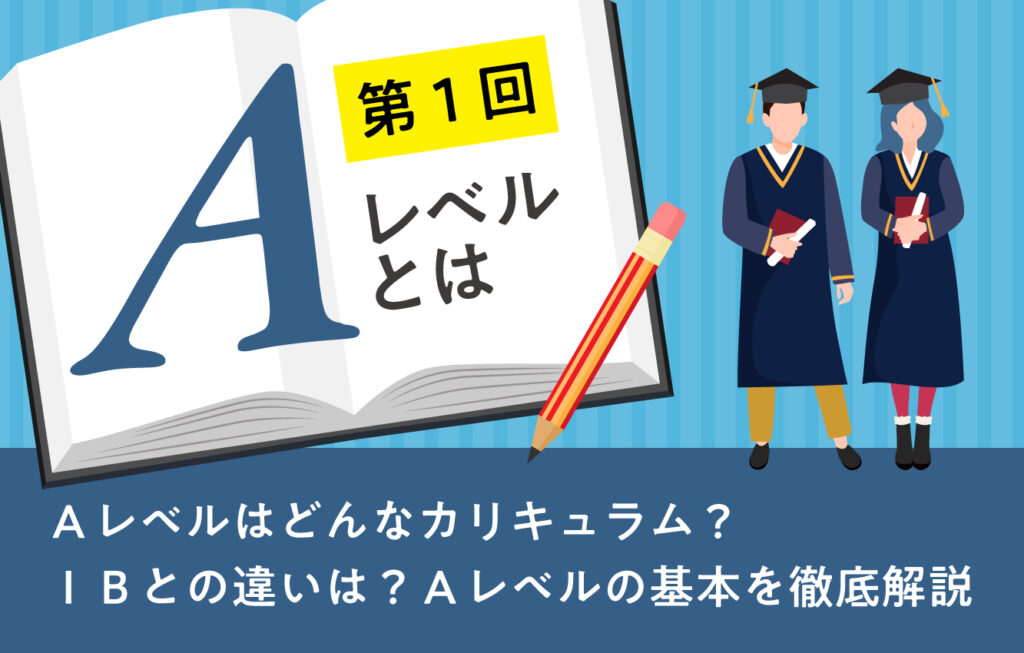【連載 日本語補習校・継承校とは?】第3回 子どもたちが日本語を学ぶ価値とは
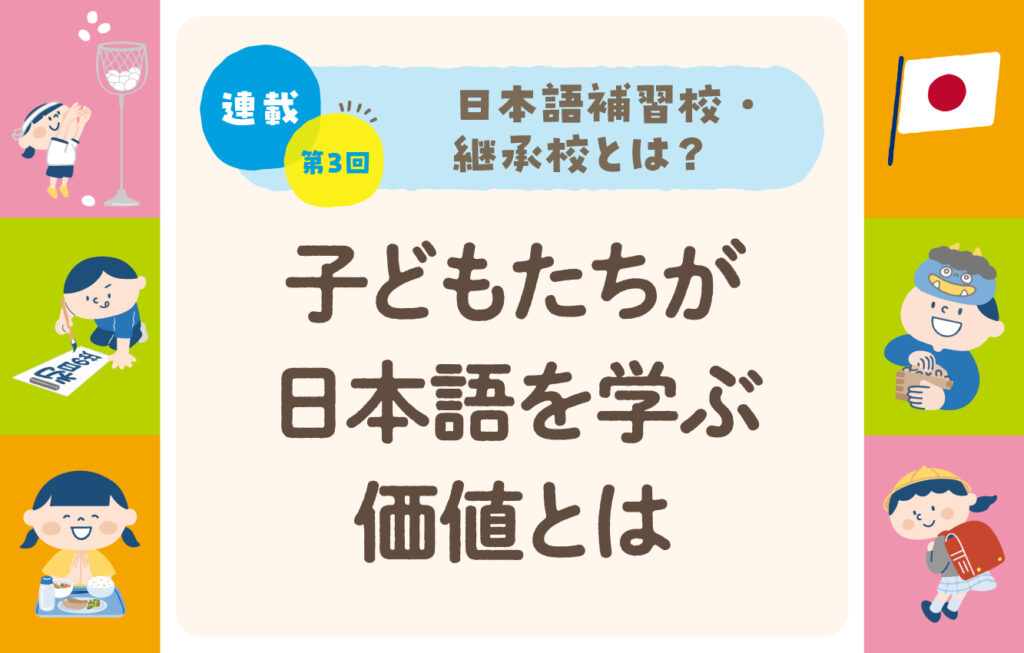
| 【連載】 【連載 日本語補習校とは?】第1回 日本語補習校とは?継承語とは?詳しい意味を徹底解説! 【連載 日本語補習校とは?】第2回 日本語補習校で学べる大切なこと~シンガポール日本語文化継承学校をご紹介~ |
しばらくご無沙汰しました磯崎みどりです。1月の第二回「シンガポール日本語文化継承学校」の取り組みについての説明の後、IB受験生への対応を抱え、記事を書く時間が見つけられませんでした。ようやく春休みが目前に見えてきたことで、引き続き掲載を続けていきたいと思います。
第三回では、世界の中で日本語を「継承語」として引き継いでいく子どもたちの増加と補習校の模索、そして継承語として日本語を子どもに「学ばせる」意義について書いていきたいと思います。
継承語の子どもたちの増加と補習校の模索
現在、継承語として日本語を使用することになる子どもたちが増加していることから、日本政府が「日本に繋がる子どもたち」として、「補習校」に通学していない、もしくは日本語学習の場を確保するのが難しい子どもたちにも、何らかの形で日本語に触れる機会を持てるような取り組みを始めています。
戦後、日本から海外に(最初はアメリカ)家族を帯同して出向する日本人の家庭の子女に日本語学習の機会を与えることが目的であった「補習校」は、少しずつその存在理由が現状と合わなくなってきていることもあり、補習校の方も改革を進めてきています。
私は以前補習校の教員でもあったことから、「補習校ネット」という、補習校情報の交換会に参加しており、政府の肝いりで「補習校」の姿を現状に合うものに変えていこうとする取り組みにも興味を持っていますが、根本的な部分で継承語の子どもたちが補習校で学ぶことが合わないものになっている大きな理由があると考えています。
それは家族を帯同する日本人家庭の移動の仕方の変化です。私はシンガポールに居を構え始めてから、まもなく4半世紀になりますが、この25年の間にもシンガポールに住む日本人社会の様相が違ってきていることを感じています。
一つ目は幼いお子さまを持つご家庭が増えたという印象があるということです。そして二つ目の、シンガポールを皮切りに次々と別の国に移動する海外要員の方々が増えていることは注目に値します。何十年か前の、日本と海外を行ったり来たりする就労形態ではなくなったご家族が増加したことから、海外に長期に滞在する子どもたちが増えていると感じられます。
そうなると、補習校の最大の目的である「日本の学校に戻って困らない日本語力を身に着けておくこと」がその子女の日本語学習目標ではなくなってきている家庭も増えていると言えるでしょう。子どもたちの日本語については、シンガポールの現地校やインター校に合った日本語の学びが必要となることから、各ご家庭で目的がさまざまになることが避けられなくなってきたのではないでしょうか。
こういった、家族の姿、そして働き方の変化の中で、文科省管轄の「補習校」での学びが長期滞在の子どもたちを育てるには適合しない場面に繋がることがあるのです。シンガポールだけに限らず、世界中に同様の駐在員家族が増えていることに加え、現地の方々と婚姻関係を結ぶ中で生まれた日本に繋がる子女にとっては、その地が子どもたちにとって母国である場合ももちろん増えていて、そういった子どもたちにとっては、なおさら、日本語を学習する目的は日本への帰国ではないのです。
ただ、シンガポールの学習形態・学習への保護者の意欲の特徴として挙げられるのは、ローカル校(現地校)であろうと、インター校(国際校)であろうと、すでに家庭内でしか使用していない言語を、確実に学習にも使用できることを求められる、もしくは求めたい保護者が多いということです。
つまり、日本語に触れる機会も日本で生活するよりは少なく、子どもたちが日本語を使用できる場面が少ない状況にありながらも、保護者は第一母語と同じレベルで日本語を学習させておきたいと考える状況が生まれることで、子どもと保護者の間の思いの乖離が見られるのも、継承語として日本語を使用する子どもたち・ご家庭によく見られる現象です。
「補習校」の基本的な指導内容が、文科省検定教科書を指導要領に沿って指導することが中心である以上、海外に長期滞在し、日本が本帰国先でない子どもたちの多くに見られる、日本語が継承語となっている場合に、教科書を指導要領通りに学習するのが難しいケースも見られます。そういった意味では、「補習校」が海外長期滞在者にも指導の目を向けるのであれば、その内容には改革が必要だと言えます。
では、そんな継承語となっている日本語を、学習レベルとしていく意義はどこにあるのでしょうか。次は、その意義について考えてみたいと思います。
継承語となっている日本語を子どもに「学ばせる」意義
継承語の定義については第一回でも書きましたが、まずはその定義についてもう一度振り返ってみたいと思います。継承語とは、親や家族などから受け継がれる言語で、第二の母語とも呼ばれる言語です。国際結婚や家族の移動などによって言語環境が違う社会に暮らす子どもが、家庭などで使う言語のことを指しますが、親の母語であり、アイデンティティの形成にとって大切な言語です。
ただ、使われる場が家庭内など狭いことが多く、継承語の力の発達は限られてしまうことが多いのが実情です。また、その言語の社会的認知度の高い低いによって、価値が違ってくるものなのですが、ありがたいことに、シンガポールにおける日本語の位置づけは大変高く、外国語としても学びたい言語の一つになっています。そんな言語ですから、「子どもに学ばせる意義」を挨拶ができる程度でいいと考える保護者は少なく、英語とともに第一言語にしておきたいという思いを持つご家庭が多いように見受けられます。
子どもたちの継承語としての日本語の使用頻度、日本語への思いの強弱は多様であるものの、継承語として日本語を使用できることは、日本文化への理解を育て、自らの日本のルーツへの誇りを育てることができます。したがって、継承語である日本語を読み書きできる学習に使用できるレベルまで学び続けることで、いわゆる大人になっても使用できる言語に変換させ、社会で必要とされる日本語を使いこなすことができるようになれば、将来的には異なる文化との橋渡しとしての役割を果たすことに繋がることは間違いありません。
各家庭によって、求めるレベルがまちまちであることから、もう日本語は必要ないとされることもあるでしょう。しかし、言語はアイデンティティーと強く結びつくものであり、その重要性を理解することが、子ども自身の精神的成長の中での気づきになるように、その習得を促したいものです。
次回は、補習校・継承校最終回として、これまでの回で書きそびれたことなどを書き、まとめとしたいです。
磯崎みどり氏ご紹介

継承日本語指導者として、20年以上の実績を誇り、アメリカコロンビア大学大学院で継承語について研究、修士課程を修了。
アメリカ、シンガポールの補習校指導を皮きりに、現在シンガポール日本語文化継承学校校長。また、IBDP認定指導員として、日本語文学(Japanese A Literature)を指導。シンガポールではAIS(オーストラリアンインターナショナルスクール)でIBDP日本語文学、IGCSE相当の母語日本語、Tanglin Trust SchoolでGCSE、A Level日本語を指導。その他、Marlbourough College (Malaysia)のIB Japanese A LiteratureのSSST (School Supported Self Taught)を指導。
英語指導については、シンガポール日本人学校中学部の英会話クラス講師、早稲田渋谷シンガポール校英語教員を歴任。
自身がマルチリンガルの娘を育て上げた母親の一人。
日本語文化継承学校は、日本国籍をもちながらも、海外生活が長く、早急な日本への帰国予定がない、もしくはシンガポールに永住する子供たちを主な対象とした、日本語と文化の両面から学ぶことを目的とした学校です。さまざまな環境の子どもたちにあった学びの場を提供するため、日本語文化継承学校はさまざまなコースを開催しています。
詳しくは、ホームページへ
日本語文化継承学校の日本語教師募集
継承学校は、継承語として日本語を学ぶ子どもたちを応援する学校です。
一緒にそういった子どもたちを指導してくださる教員を募集しています。
詳細を知りたい方は、sjkeisho@yahoo.co.jp にご連絡ください。
●記事内容は執筆時点の情報に基づきます。
【関連記事】