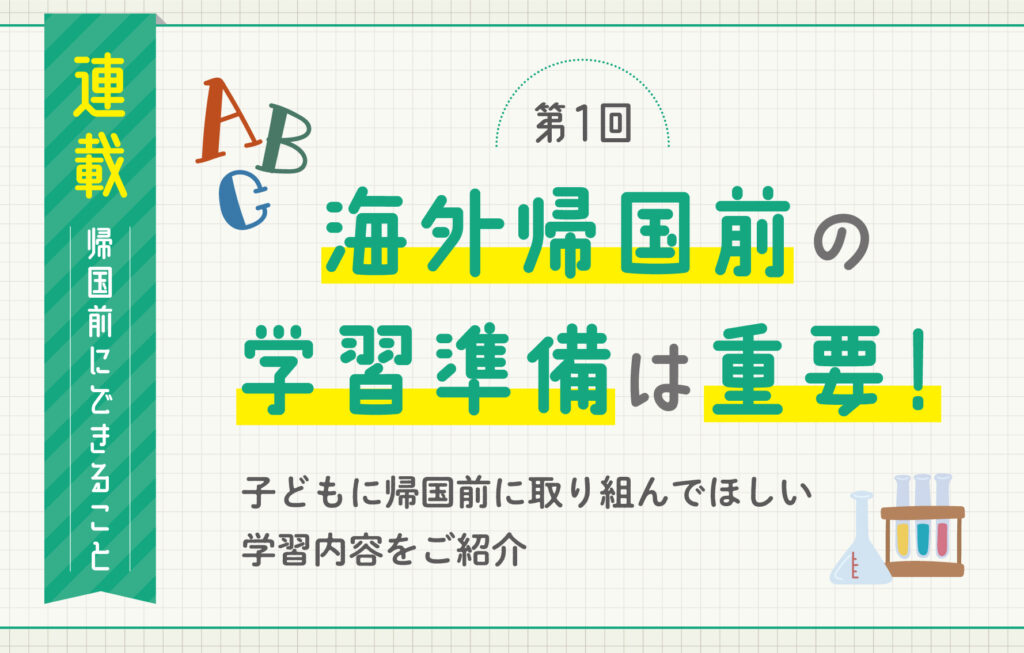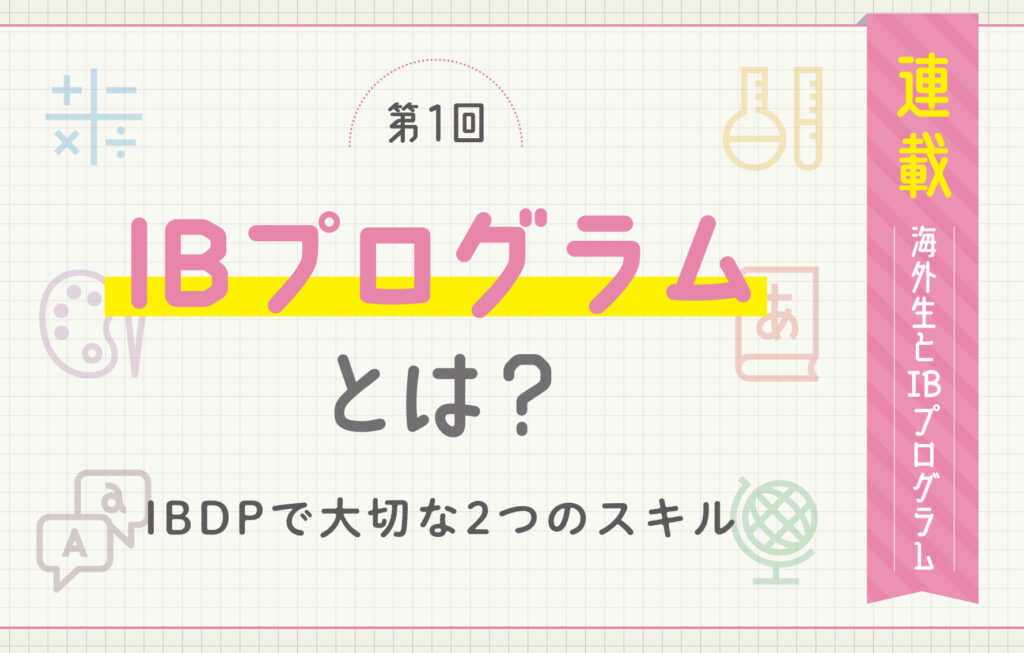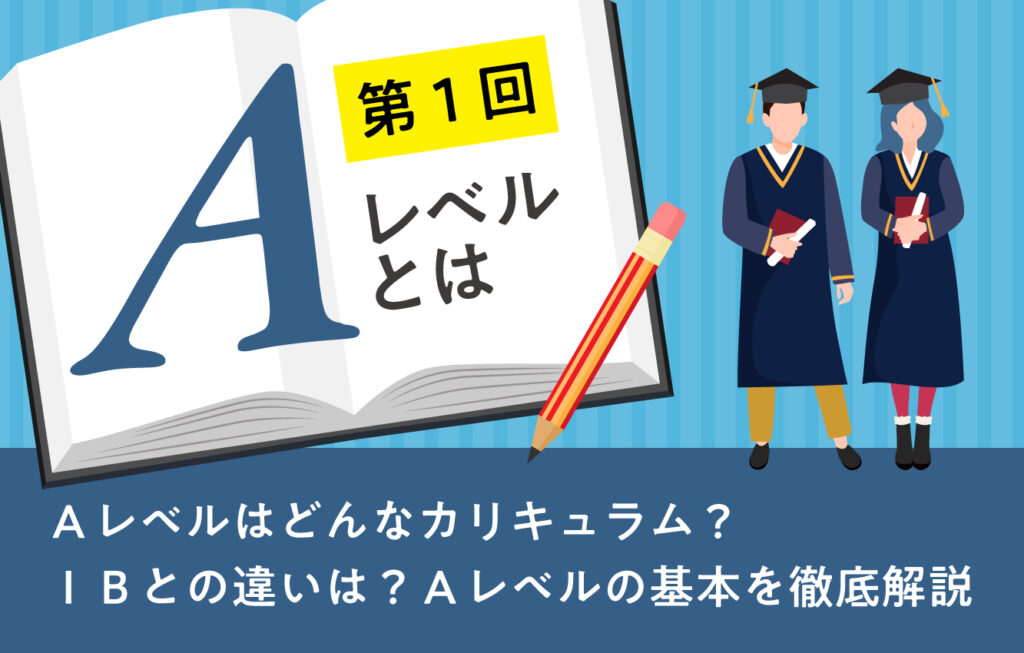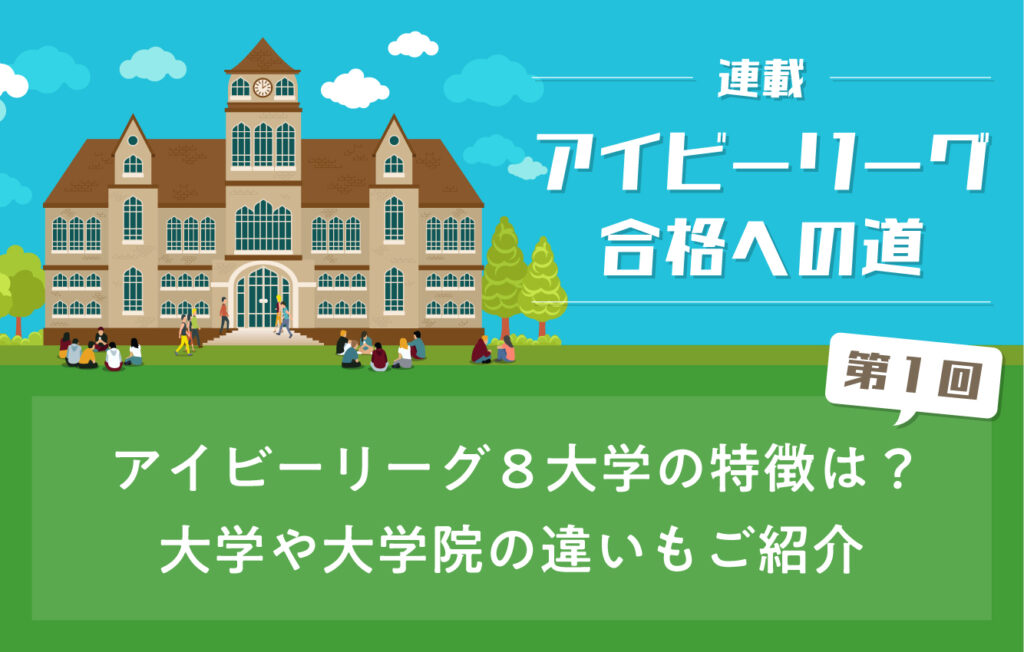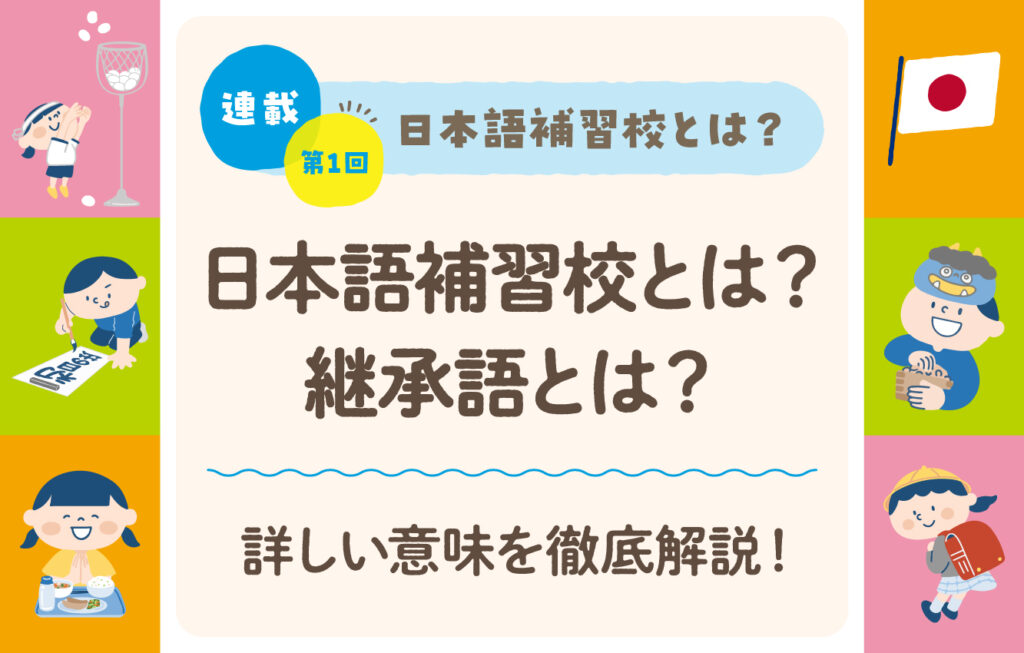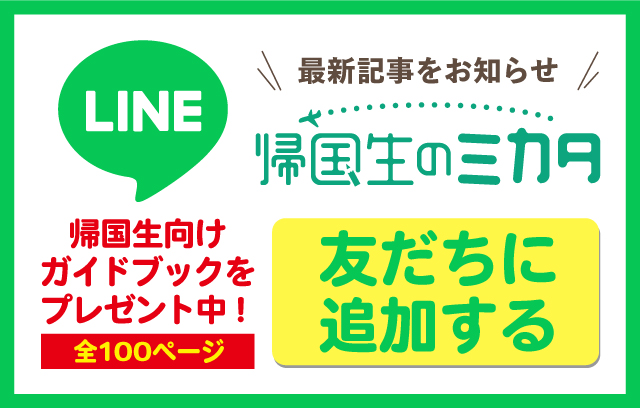【連載第2回 おうち英語】子どもの英語習得!知っておきたい親の関わり方
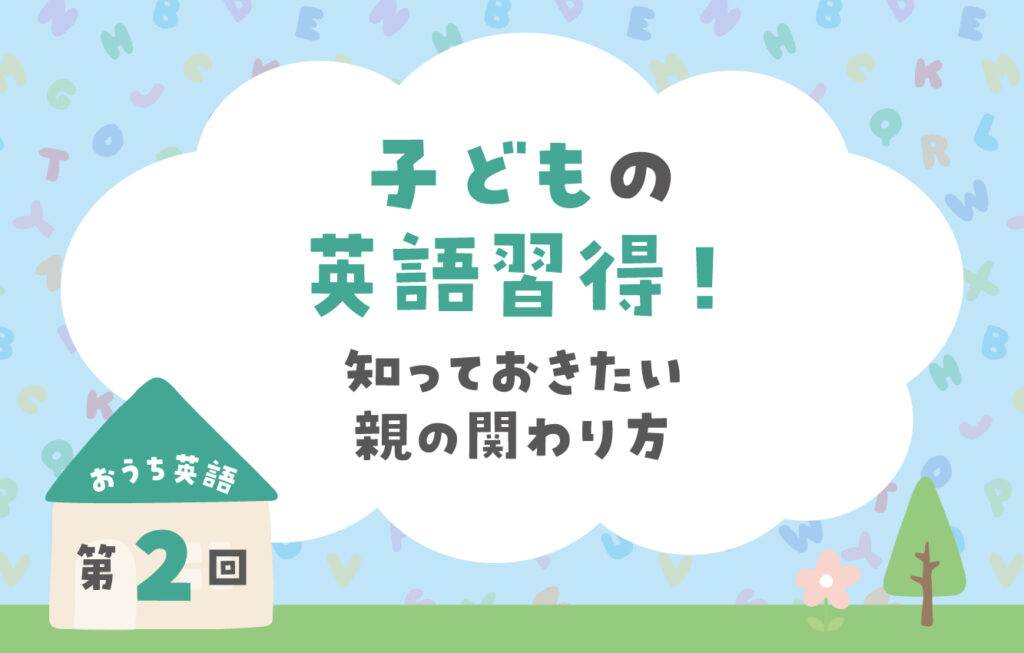
磯崎みどりです。連載第1回目の結論として、家庭では 「英語は楽しい」、「間違えても大丈夫」という前向きな雰囲気を作ってあげることの重要性を挙げました。そして、第2回目では、親として具体的にどのように子どもの英語習得に関わっていくべきか、そしてどの程度の習得レベルを目指すのがよいのかについて書いていきます。
おうち英語とは?
今回の連載でタイトルとして使われた「おうち英語」という言葉は、私は実はこの連載を書いてほしいと連絡を受けた際に初めて知り、その後YouTubeで「おうち英語」を実践されている方の映像を見て、これを「おうち英語」と呼んでいるのだと知った次第です。思い出してみると、私も家庭で「おうち英語」を実践した母の一人であると考えてよいのだろうと気づきました。その経験も元に書いていこうと思います。
そもそも「おうち英語」は公式にどのように定義されているのかはわかりませんが、私なりの「おうち英語」の定義は、「日本で生活しながら、家庭の中で子どもの習得を狙って英語を使用できるようにすること」と捉えました。この定義をもとにお話を進めていきたいと思います。
おうち英語はいつから始めるべき?
「おうち英語」という言葉を聞いたとたん、「おうち英語はいつから始めるべきでしょうか?」という質問が返ってきそうですね。英語の音に慣れさせるなら、早い時期から始めたらよいと思いますが、習得できるものとできないものがあることをよく理解した上で進めていただく必要があります。
まずは習得できるものについて。第1回目にも書いたように、耳を慣れさせるためには幼い頃から英語を聞かせておくと、音には慣れます。その量が多ければ多いほど、始める時期は早ければ早いほど、音の通り真似をすることができるようになるのは間違いないです。
ただし、その言葉の意味まで分かるかというと別の話です。
◆我が家の経験談
我が家の話をしましょう。娘は米国で人権弁護士として、そして法廷弁護士として、そして、現在では法学の研究者として法律の専門的な文書を発行する仕事に加え、ニューヨーク大学法科大学院で准教授としても指導に当たっているように、現在、英語のみを使って生活していますが、生まれたのは日本で日本国籍のみを有しています。
彼女が生まれる時には、すでにその後近いうちに米国に移動することになるとわかっていたこともあり、英語の音は聞かせたいと思い、夫が米国出張をするたびにディズニービデオは英語版を購入し、見せていました。画像とともに英語で話すビデオからは、少しずつ音をピックアップし、1歳になる頃には毎日英語版を見て、いくつかの言葉を真似するようになっていました。いくつかの語彙は、音として聞き取れていたことを表します。
しかし、間もなく2歳になろうとするある日、突然、いつも見ていた「ライオンキング」のシンバの台詞を聞いたとたん、「なにか知らないこと言った。」と英語の内容がわからないと言い始めました。
それまでは画像だけを見て理解していたのでしょう。場面場面で音を真似するだけでなく、日本語の言葉が少しずつ増えていく中で、日本語でビデオのストーリーを自分の言葉で説明をするようになっていたのですが、(これはよく幼児が絵本の絵を見て、文字が読めるわけではないけれども、その絵から自分でストーリーを語り始めるのと同じです。)ある時からこのビデオでは意味の分からない言葉が流れてくる、と気づいたのです。
私は学部生の時に発達心理学を専攻し、子どもの言葉の発達についても研究していましたが、その時にはバイリンガル研究を行っていたのではなく、日本人の子どもの日本語習得の発達について研究していただけなので、2言語の習得については知識がありませんでした。
しかし、コロンビア大学大学院で継承語および第2言語習得について学んだ際に、まさに娘の見せた現象は、意味のある気づきであると知りました。つまり、彼女は2歳の段階ですでに日本語の語彙・文法については理解をしていたことから、ビデオから流れてくる言語は、自分の知る言語ではないと気づいたのです。おしゃべりの早い子どもだったことから、この言語の違いへの気づきもかなり早かったのだ、と後で知ることになりました。
私はこの時、言語の違いを知るだけでよいと思っていたので、娘に英語をもっと聞かせて習得させようとはしませんでした。後に英語の生活になることがわかっていたからです。音には慣れさせておきたかったけれど、今は日本語の方が大切な時期だと考えていたので、「おうち英語」はなんとなくわかるストーリーを聞かせて見せるだけにとどめました。それが良かったということは、渡米してからわかるデメリットとなりうる話を後に紹介しますが、この時点の様子からは、英語を聞かせているだけでは使える言語として習得はできないことは明白ですね。
私の娘の場合は、完全なモノリンガルの環境で育ったため、しっかりと日本語の語彙は習得していたものの、英語のビデオを見せているだけでは、音として聞こえてくる言語の意味が分かるようにはなっていなかったのです。
デメリットという語彙を使ってしまうと、問題のように感じられるかもしれませんが、問題というほどではないにしても、2言語が同時に入ってくることにより、2言語が混ざってしまうことがあるのは間違いありません。この現象により、言語習得が遅滞しているように見える状況があり得るということはデメリットととらえられる可能性があるということです。
バイリンガル環境で育つ子どもは、言語習得が遅滞すると思われていた時代がありました。現在ではさまざまな研究によってこれは言語障害や遅滞ではなく、2つの言語のそれぞれで習得している語彙数を合算すると、モノリンガルの子どもの習得した語彙数とほぼ同じであることがわかっています。2つの言語にふれる環境が言語発達遅滞の原因になることはないのです。(Baker & Wright, 2021, p. 96)。
ただ、入ってくる情報量の多寡によって、どちらかの言語の方が語彙数が多くなるのは間違いないことであるのと同時に、早ければ早いほど、音は捉えられるようにはなるけれど、言語習得が簡単になるとは限らないことを証明している例としてお伝えできます。
◆あるご家庭の経験談
そして、「渡米してからわかるデメリットとなりうる話」もここで紹介します。我が家は娘が3歳の時に渡米することになったのですが、周囲にいらした、滞米日本人ご家庭におけるお子さま方の英語習得と日本語の習得について、気づいたことを書きたいと思います。
日本人ご家庭Aでは、ご主人が英語を担当され、奥様が日本語を担当するというように、国際結婚家庭と同じように娘様に話し掛ける言語担当を振り分けられていました。
奥様は日本語で常に話し、読み聞かせも日本語、ご主人は話しかける言語も英語、読み聞かせも英語といったように、担当をきっちりと分けておられ、米国で娘様が生まれたときからずっとそれを続けてこられていたと聞きました。
ところがある日、その娘様が通う米国の幼稚園の先生から、英語をまったく理解していない、と言われてしまいます。当時まだ4歳だった娘様は、幼稚園で使用されるような呼びかけなどの語彙は日本語でしか習得していなかったのかもしれません。
また、別の日本人ご家庭Bでは、娘様(当時3歳)は日本語の発音まで英語的になっているので何を言っているのかわからないことがあると笑っておられました。その娘様も生まれて間もなく渡米されていました。
どちらのケースも、まだお子様が幼く、日本語も確立しないうちに英語での生活になったことで、わかっていない、とされたり、発音が言語間で混ざる、という現象が起きていました。ですから、早ければ早いほど英語と日本語両言語の習得は簡単で、英語を聞かせておけばいいというのはまったくの間違いであることがわかる例と言えるでしょう。
親はどの程度「おうち英語」の習得に関わればよい?
では親としてはどのように関わっていけばよいか、ということなのですが、なにより、子どもには、まず軸となる言語をしっかりと習得させてあげましょう。そして、2言語以上の言語が生活内にあるなら、その軸となる言語ともう一方の言語を結びつける役割を果たしてあげることで子どもの二言語の理解が進み、「おうち英語」を習得していくことができるでしょう。
その方法として、私が一番効果があると考えるのは、日英の読み聞かせです。英語の本を読み聞かせした後、日本語に翻訳し、内容を日本語で伝えることは、大変効果的です。
実際、覚えるまで同じ本を繰り返し読み聞かせることは、私がやっていた取り組みです。渡米した時には、英語の音は聞いたことがあったものの、内容は理解できる状態ではなかった娘に、繰り返し好きな英語の本を英語→日本語翻訳の順に読み聞かせを続けました。
それに加えて、幼稚園で英語で習ってくる内容や言葉を日本語で説明し、日本語に置き換えて理解させ、英語と日本語を結び付ける作業に毎日取り組みました。我が家の状況は、日本にいながらにして英語を習得させようとする「おうち英語」とは少し違った状況ではありますが、まだ英語に慣れない娘を一日中言葉の分からない世界に置き去りにするのが忍びなく、週に2回だけ、2~3時間だけ幼稚園に通わせていたので、状況はかなり「おうち英語」に近い状態だと言えます。
幼稚園では英語ネイティブ話者の英語を聞き、家では私と英語と日本語を結び付ける絵本の読み聞かせを聞き、家庭内の生活は日本語という状況だったからです。親は、子どもの2言語(以上)の言語習得度を理解し、その言語間のバランスを見守り、確認できることが重要だと考えます。
まとめ
まったく英語を理解できず話せなかった娘が、長じてからは英語で専門性の高い仕事をこなし、その上で、一度も日本の幼稚園や学校には通ったことがない中(体験には数回行きましたが)、高校卒業の際には、バイリンガルであることを証明するバイリンガルディプロマを手にし、法科大学院では日本の法律についても研究することができるレベルで日本語を保持できるようになっていくまでの歩みについては、海外子育ての連載に詳細を見送るとして、ここではもう一度親の関わりについて話を戻したいと思います。
バイリンガルにはレベルがあるため、その詳細については別の機会に譲るとして、いわゆるバイリンガルに近づくには次のように親が支援の手を差し伸べるのが良いと結論付けられます。
| ⅰ)英語を習得するには、学び始める時期が早ければ早いほど良いと考えるのは間違っていることを知ろう。 音を聞けるようにはなり、そのまま真似をすることはできますが、それで英語をペラペラに話せるようにはならないことを知り、音に慣れさせるつもりで英語を聞かせておきましょう。そして、少なくとも軸となる言語(日本人のご家庭の場合は日本語)がある程度確立するまでは、無理に英語を習わせようと考えないことだと思います。 |
| ⅱ) 親は子どもの2言語間バランスを常に確認し、2言語間をつなぐ役割を果たそう。 そのためには、日本人の保護者であれば日本語は母語であると考えられますが、英語もある一定以上の知識がないなら、「おうち英語」は成功しないだろうと考えます。英語で生活する環境が整っているなら別として、子どもが英語で会話レベルの内容を話すの聞いて、「うちの子、英語がすごい」と思ってしまうこともあるかもしれませんが、保護者自身の英語力に自信がない場合は、無理に教えようとしない方がよいでしょう。訂正することが難しい場合は、英語ネイティブのビデオ画像や、音源などを聞かせるのがよいと考えます。 |
次回3回目は、どの程度の英語習得が必要なのかという疑問について考えてみたいと思います。
参考文献:Baker, C., & Wright, W. E. (2021). Foundations of bilingual education and bilingualism (7th ed.). Multilingual Matters. Bristol, UK: Multilingual Matters.
磯崎みどり氏のご紹介

継承日本語指導者として、20年以上の実績を誇り、アメリカコロンビア大学大学院で継承語について研究、修士課程を修了。
アメリカ、シンガポールの補習校指導を皮きりに、現在シンガポール日本語文化継承学校校長。また、IBDP認定指導員として、日本語文学(Japanese A Literature)を指導。シンガポールではAIS(オーストラリアンインターナショナルスクール)でIBDP日本語文学、IGCSE相当の母語日本語、Tanglin Trust SchoolでGCSE、A Level日本語を指導。その他、Marlbourough College (Malaysia)のIB Japanese A LiteratureのSSST (School Supported Self Taught)を指導。
英語指導については、シンガポール日本人学校中学部の英会話クラス講師、早稲田渋谷シンガポール校英語教員を歴任。
自身がマルチリンガルの娘を育て上げた母親の一人。
日本語文化継承学校は、日本国籍をもちながらも、海外生活が長く、早急な日本への帰国予定がない、もしくはシンガポールに永住する子供たちを主な対象とした、日本語と文化の両面から学ぶことを目的とした学校です。さまざまな環境の子どもたちにあった学びの場を提供するため、日本語文化継承学校はさまざまなコースを開催しています。
詳しくは、ホームページへ
●記事内容は執筆時点の情報に基づきます。
【関連記事】
最新情報をLINEとメルマガでお届けしています!ぜひお友だち追加・フォローしてください。